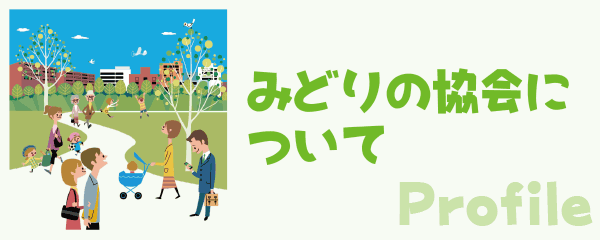草花編
クリスマスローズはキンポウゲ科の宿根草で、本来はクリスマスの頃に白い花を咲かせるニゲル種のみを指しますが、日本では春先に咲くオリエンタリス種などに代表される ヘレボルス属すべての植物を指します。
開花期は12月~4月。花弁のように見えるのは萼片で、花後も2ヶ月以上も花弁の状態を保つため、長く楽しむことができます。多くは常緑ですが、高温多湿の気候は苦手で、夏の休眠期に葉が枯れるものもあります。夏は強い日差しと高温となる場所を避け、秋から冬は日あたりを確保できる落葉樹の下が植栽場所に適しています。そのような場所が確保できない場合は、鉢で管理すると季節にあわせて移動が可能なのでおすすめです♪種をつけたままでも生育にあまり影響はありませんが、 鑑賞性がないと思われたときには花がらを摘み取ります。また、霜が降りるようになる頃に新しい葉が展開するので、古い葉は切り取っておくとよいです。
冬から早春の彩が少ない時期にも草花を楽しむことができるようにと、クリスマスローズを植栽してみてはいかがですか。

ハスもスイレンも水底の土や泥の中に根を張り、水の上に葉を出し、花が咲きます。
水面よりも高く茎を伸ばして葉や花を咲かすのがハス、水面で浮くように葉や花を咲かすのがスイレンです。他にも、スイレンの葉には切込みがありますが、ハスの葉にはありません。
ハスの花は早朝に開いて昼に閉じるのを繰り返し、4日目に花びらが散ってしまいます。その花びらの散った後の花托(かたく)が昆虫のハチの巣に似ていることから、「ハチス」と呼ばれているそうです。また、食べるとおいしいレンコンはハスの地下茎のことですが、食べられるのは食用のハスであり、観賞用の花ハスは小さくて食べることはできません。
スイレンも花が開いて閉じるのを3日間繰り返し、その姿が眠っているように見えることから「睡(ねむる)蓮(はす)」つまり「睡蓮」と呼ばれたそうです。咲き終わったスイレンは、花びらを散らすことなく水中に没していきます。モネの睡蓮が有名ですね。また、スイレンには、温帯性スイレンと熱帯性スイレンがあり、原産地、花の色、咲き方、耐寒性などに違いがあります。日本の原種は温帯性スイレンの仲間に入ります。熱帯性スイレンは水面より高いところに花が咲き、花の色が鮮やかなものが多いです。


ハス ハスの花托
-300x241.jpg)
-300x233.jpg)
温帯性スイレン(徳川園) 熱帯性スイレン(久屋大通庭園)
お彼岸の頃に咲くので「彼岸花(ひがんばな)」と呼ばれ、別名に「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」やヒガンバナ科を総称した「リコリス」があります。
現在の日本のヒガンバナは、中国より渡来した個体の球根から増えていきました。
日本で見られる赤い彼岸花は、種子はできず、球根が分かれて増えていきます。ただ、同じ「ヒガンバナ科」の中でも、種をつくり、種を植えて増やせる品種もあります。
花の色には、代表的な赤の他に、白、黄色、ピンク、オレンジなどがあります。
古来より「葉見ず花見ず」と言われるように、花が咲き終わってから、おおよそ晩秋から初冬が近づくと葉が出てきます。その後、冬の間に栄養を蓄え春に葉が消えてしまいます。
ヒガンバナの分球は、葉を出している間は活発に成長していますので、葉がある時期に球根は掘り上げず、5~6月頃に葉が枯れた後に掘り上げるのが良いです。
すぐに植え替える場合は白い髭のような根を触らず植え、すぐに植えない場合は根を切り取っても問題ありません。移植の場合は、周辺の土壌ごと大きく掘り取った方が根を傷めず良いです。
-287x300.jpg)
-285x300.jpg)
ヒガンバナ(庄内緑地) ヒガンバナ(徳川園)
-239x300.jpg)
-201x300.jpg)
白いヒガンバナ(荒子川公園) ヒガンバナ科タヌキノカミソリ(東谷山フルーツパーク)
冬の代表花のシクラメン。
街の景色が冬色に替わる頃、あちこちの花壇やお庭でシクラメンを見かけるようになります。
さて、シクラメンとガーデンシクラメン、同じようで同じではないことを知っていますか。
シクラメンは、冬の女王といわれる花です。そして、ガーデンシクラメンは、そのシクラメンの中でも特に寒さに強いものを交配して作った品種で、霜にあたっても枯れないため冬のガーデニングの定番になっています。ただし、マイナス5度以下になると枯れてしまうので、植える場所には注意が必要です。
また、ミニシクラメンと呼ばれているものは、シクラメンを小さく仕立てたもので、見た目はガーデンシクラメンと同じですが、霜に当たると枯れてしまいます。
シクラメンは、株が大きいので、一目で分かりますが、ガーデンシクラメンとミニシクラメンは見た目にはかわりません。名札をみて分かる程度ですので、花苗を購入する際はお間違えのないように。

艶のあるピンク色
公園や庭などで、つるを伸ばして他の草木にからみついている植物をよく見かけます。これらは「つる性の植物」で生長が旺盛、地上部のつるを取り去っても地下部分の根が残っているので、何度でも芽を出します。代表的なものに、他の植物に覆いかぶさってそれらの「やぶ」をも枯らしてしまうということでヤブガラシ(ビンボウカズラとも)という名をもつ植物がいます。やっかいものの植物ですが、ハチや蝶にとっては大事な「蜜源」となっています。ヤブガラシの他につる性の植物には、ヒルガオ科のヒルガオ、アカネ科のヘクソカズラ、ガガイモ科のガガイモなどが身近な場所で見られます。


ヤブガラシ(蝶が蜜を吸いにきている) ヒルガオの花


ヘクソカズラの花 ガガイモの花
日に日に涼しくなったり、日暮れが早くなったり、雲が空高く流れていたり。10月になって、様々な場面で秋の気配を感じられるようになりました。
コスモスは漢名「秋桜」のとおり、秋の訪れを知らせる代表的な花です。
花色は濃いピンク色、淡いピンク色、白色が一般的ですが、最近では黄色いコスモスもよく見かけるようになりました。この黄色いコスモスは、大学の研究室が開発した品種であることをご存知ですか?
1957年(昭和32年)、玉川大学農学部育種学研究室の佐俣淑彦教授が紅系のコスモスの中に、突然変異で黄色く発色した株を発見しました。
その株をもとに20年以上にわたって交配実験を繰り返し行い、より黄色味を帯びた株の選抜に取り組み、1980年(昭和55年)頃から鮮やかな黄色い花の定着に成功しました。
そして、1987年(昭和62年)に種苗法に基づいて世界初の黄色いコスモス「イエローガーデン」として登録がなされました。
その後、さらに改良が進み、咲き始めは白く、気温が下がるにつれて黄色が濃くなるコスモスが開発され、「イエローキャンパス」という品種名で多くの人の目を楽しませています。
大学から生まれただけに、「キャンパス」と名付けられたのでしょうか。
(引用:玉川学園の歴史)

ピンクコスモスとイエローキャンパス
熱帯性スイレンは、従来の温帯性(耐寒性)スイレンと比べ、たくさんの花を咲かせてくれます。熱帯性スイレンの花色は、青、紫、ピンク、白など。エキゾチックなムード漂う花は、暑い夏によく似合います。アフリカ原産のためか、暑さが大好きで、水温が40度になっても元気に咲いています。花の種類によっては豊かな甘い香りがあり、花色とともに香りも楽しんでいただけます。香りをかぐときはくれぐれも水に落ちないよう気をつけてくださいね。
草花編「ハスとスイレン」にも書いてあるように、花は朝開いて夕方には閉じる、この開閉を3日間繰り返した後に、閉じたものは水没します。
その3日間、毎日変わる花の表情にも注目ください。一日目は花の中心にある黄色い雌しべが見えます。二日目になると、雄しべが雌しべをドーム状になって覆い、中が見えなくなります。三日目は、固まっていた雄しべが少し開き気味になっています。この花の表情の変化も熱帯性スイレンの魅力だと思います。
夏の花と思われがちな熱帯性スイレンですが、実は初夏から秋にかけて楽しむことができます。
寒さで生育が止まる11月近くまで花を楽しめますので、暑さが過ぎたあたりにのんびり花を見に公園に足を運んでみてください。
-300x224.jpg) スイレン
スイレン
-300x224.jpg) 1日目
1日目
-300x224.jpg) 2日目
2日目
-300x224.jpg) 3日目
3日目
熱帯スイレンが見られる公園
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
久屋大通庭園フラリエ 徳川園
-251x300.jpg)
みどりが丘公園